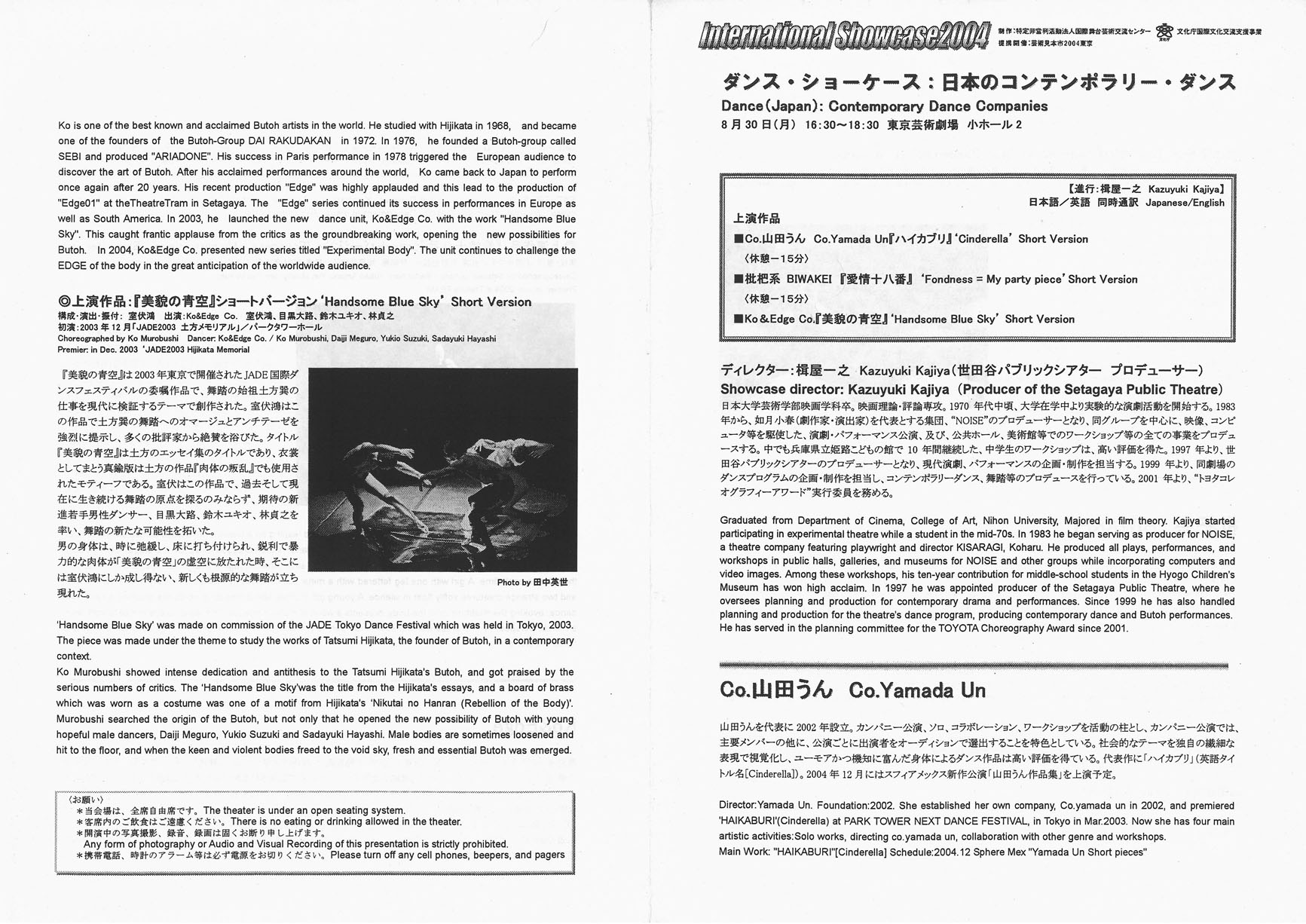
望めることと望みえないこととの間で震える境界線が踊る
木村覚
昨年から今年にかけて開催された「肉体のシュルレアリスム 舞踏家土方巽抄」展(川崎市立岡本太郎美術館)は、ひとりの踊り手の汲み尽くしえない多面性の一端を現代に蘇らせた。「土方巽」という多様体はいまでもなお未知の読解を誘発する、身体のための豊かなテクストなのだ、そう確信した。細江英公らによる写真や本人の遺した言葉などの展示パネルが伝えるこの踊り手の有様に、見ているうち、踊り手でも何でもない私のからださえも、もぞもぞと勝手に動き出し抑えられなくなってしまう。そんな出来事に土方の現代的リアリティーを実感した。当時(60〜70年代)も、おそらく同様の感覚が熱狂の渦を巻き起こしていたに違いない。踊り手たちばかりか、美術家、詩人、小説家など異分野の者たちを巻き込み、相互に刺激を吸ったり吐いたりしながら、土方はそこに生じた多種多彩な問題をひとつ、からだが動く(踊る)という一点へと収斂させ、そしてそれらを肉体という舞台のなかで炸裂させようとしたのだった。
それは果敢な冒険であった。だから「土方巽」とはすなわち冒険のテクストであり、その成功と失敗のドキュメントでもある。極点において、みずからの踊りを封印する事態にまでいたる彼の挑戦は、踊ることへの真摯な態度ゆえにいまだ強い力を発揮しうる可能性があるのだ。だからたんなる回顧気分で読まれるべきものでも、歪められた二次文献ですまされるようなものでもけっしてない。ならば、私たちはそこからいま何を読みとるべきであろうか。何を読みとることが許されているのだろうか。
ところで、室伏鴻という舞踏家がいる。数年前日本に拠点を移すまでおもにフランスで活動していたこの男について、『美貌の青空』のなかで土方は、「新しい舞踏の、まあ発見、古い言葉でいえば、原点」と語った。4年前の即興ソロ《Edge》の衝撃は、彼に「エイリアン」「『寄生獣』に出てくる異生物」などさまざまな呼び名を与えることになる。的確だと感じるいっぽう、そういった命名行為は、遅滞のなかにある速さ、強靭さの秘める崩壊の運動、またそこに溢れる大まじめなウィットにもはや言語が痙攣を起こし、その末の破れかぶれのようにも思われた。その男が昨年末、「土方メモリアル」という企画で、『美貌の青空』の題の下、若い踊り手3人(鈴木ユキオ、林貞之、目黒大路)と4枚の真鍮板を携え、踊った。
4人の踊りはまるで、「野心的な読者によるテクスト読解の試み」のように見えた。すなわち、真鍮板は68年《肉体の叛乱》に頂点を迎える初期の舞踏への、若手との群舞は72年《四季のための二十七晩》にはじまった、「様式化」を窺わせる後期の舞踏への、オマージュであり批評に映ったからだ。
ソロ公演の室伏はしばしば身体を銀粉で輝かせる。そのとき現出する照らし/照らされる身体は、いま真鍮板という危険な相手をともなって一層複雑な乱反射に襲われる。男たちは揺さぶり叩きつけついに倒れ込み、融合しえないこの異物に可能な限り接近しようとする。それは、あらゆる他者に揺さぶられる感応板になろうとしているようにも、あらゆるもののあらわれる元の形へと戻ろうとしているようにも見える。では、そのときの身体はどう仕組まれていたのか。室伏の視点は、後期土方の傾向に対する批判を含んでいた。若手3人は鍛え上げられて一様に室伏化されるのではなかった。むしろふわふわと蝶のようにさまよい、あるいは互いの乳首に指を這わせつつ恍惚の表情へ変化する彼らの身体は、あるユルさ、曖昧さに照準が合わされているようだった。性の色香はここでは硬直ではなく弛緩へ向かう。後期土方のような徹底的なコントロールがなされる代わりに「生半可」ともいいたくなるからだが晒された。洗練、完成を拒んだこのようなトライアルは今回狙いを明確に示すまでにはいたらず、かならずしも成功したとはいい切れない。とはいえその試行錯誤に込められた、ひとつの動きへ硬直することからの回避、という課題は、舞踏を現在に駆動させるための必要不可欠なアイデアに相違なく、その解決の如何によっては、舞踏を多様体として猛り狂わせることが可能になるはずである。だからこの点には、今後大きな展開を期待したい。
舞踏(あるいはダンス)にいったい何を望むことができるのか、できないのか。その問いを、「土方巽」をどう読むかをめぐる問題のなかで格闘し続ける室伏の葛藤は、これからも続くだろう。その限り、舞踏は新たな読解を誘発する謎としての輝きを保持し続けるのである。