Haru no Saiten - un sacre du printemps
1999
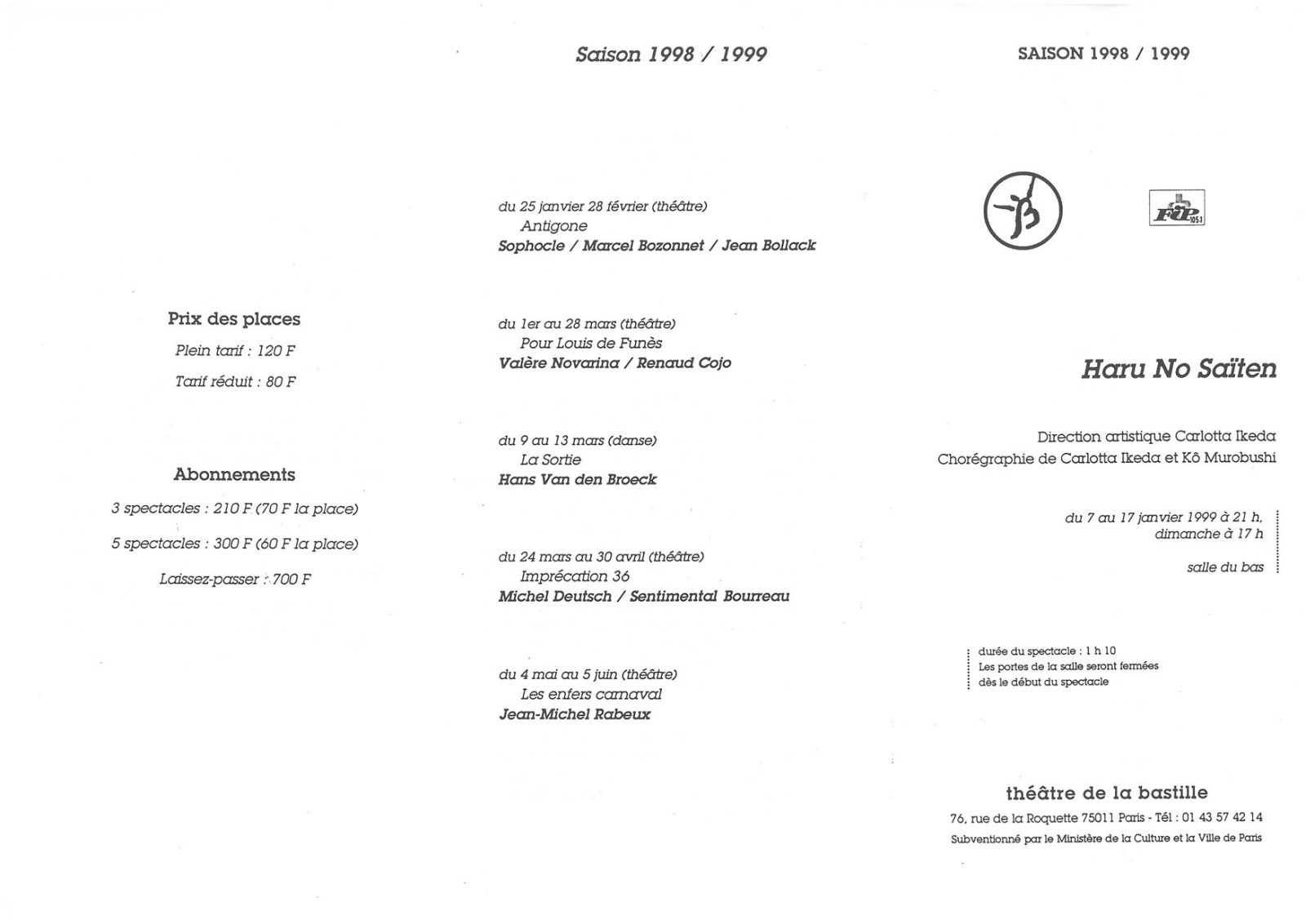
Info
- 日時
- 1999/01/07-17
- 活動内容
- 構成、演出、共同振付(室伏鴻、カルロッタ池田)
- 開催地
- Paris
- 開催国
- フランス
- 会場名
- Théâtre de la Bastille Paris
- 主催
- theatre de la Bastille
- 出演
- アリアドーネ
- 音楽
- アラン・マエ
- Coproduction
- Ariadone,Theatre de la Ville,Theatre L'Octogone de Pully(Swiss)
Description
昨年11月、『土方巽’98』(世田谷トラム)のシンポジウムで踊ったあと、すぐにフランスへ飛び「アリアドーネ」の新作『春の祭典』の振付・演出に関わり、1月のパリでの初演を終えて帰国した。その成功の様子から書く。バスティユ劇場は、バスティユ広場へ通ずるロケット通りにあって、ダンス・演劇の先鋭的なプログラムに良質の観客が集まるので有名。客席数は300に満たぬ小劇場で、ステージが客席に迫りダンサーの身体の肌理にまでとどく緊密感は踊る側には厳しいが、私が好きな劇場だ。私自身は’93年の『Ai-AMOUR』のデュオで踊って依頼ご無沙汰している。今回10回の上演の全部が満席で札止めとなって再上演の声がすでに上がっている。「ル・モンド」「リベラシオン」などが大きく取り上げ良い記事を書いた。
振付をリーダーのカルロッタ池田と共同で行ったが、ダンサーは彼女ともう一人の日本人のほかドイツ、イタリア、スペイン、リトアニア、フランスから一人ずつ混成の女性七人、音楽と照明はフランス人が担当した。
私が「アリアドーネ」のグループ新作を振付けるのは’87年のモンペリエ・ダンス初演の『HIME』以来本当に久しぶりのことで、 BUTO版『春の祭典』という話題性とともに今回の成功の大きな要因かもしれない。というのは自賛ではなく他賛である。池田と話したことだが、客席には八十年代の最初期のわれわれの観客たちが再来し、新しい世代の客と交ざって熱気を呼んでいるのがわかった。
振付は始めからニジンスキーのオリジナルのコレグラフィーにはこだわらなかった。以後のメリー・ウィグマンからベジャール、バウシュまでのヨーロッパのコレグラファーたちによる変奏についても一切これを参照することはしなかった。ただストラヴィンスキーの音楽については音楽を担当したアラン・マエと再三話し合いながら進行した。
すでに・つねに切り離され、切り刻まれ、別々のものにされた魂や身体の複数の場所から〈サクレとは何か〉と問うこと。民族的なものや民族への再帰ではなく、不可能なこと、母なる自然への回帰も超自然への帰依でもなく、別の共同性や他の共同体をうち立てる幻想でもないこと。サクリファイス、真っ平。むしろカオスの海の無数に偏在する無意味な炸裂と輝きである複数のサクレ=ノイズの幸運に即くこと。祈りが不能とされた場所でくぐもり萎えた指とふるえる膝で踊ること。痛みを聞き届けること。傷ついてボロボロの別々の言語で、切り離され切断する音階で、吃音で、問いかける声の縁と縁のギザギザをすり合せ、身体の震える断面で交差し響き合うこと。石の沈黙の声で語り、聴取不能にされた炸裂する耳で聞くこと。嗅ぐこと、動物の鼻で境界を押し広げ、わがテリトリーの外へ出ること。失語と恐怖に殉ずること。こうしたことのすべてが踊ることなら、踊りはそのプロセスそのものによって外の偶然へと、他者との出会いの幸運へと開かれているだろう。そうして踊りは他の移りゆきであり、場所を捨てる場所であり、その棄却という青空のような「異郷」への「素晴らしい放浪=途上」であるだろう。
倫理的でクリティカルな「神経の秤」のポジションだが。これは今や常識的であるだろう。私はそれを「ノマディックでヘルメックでメタリック」な放浪と混成のポジションと書いたこともある。出会いの歓び、出来事の、幸運、偶発事へと開かれたスペクタクル。
そうして、ストラヴィンスキーはコンピューターの鋭利な刃物に刻まれて、さらにメタリックで過激に変奏され、ダンサーたちの肉体に突き刺さった。肉体は「沈黙=叫び」「水銀の雲海」に「ゆらぎ」波形になり、雲の動物やカスミの鳥、鉱物の花になる変形と放浪を生きた。
- translation
- 編集:渡辺喜美子
